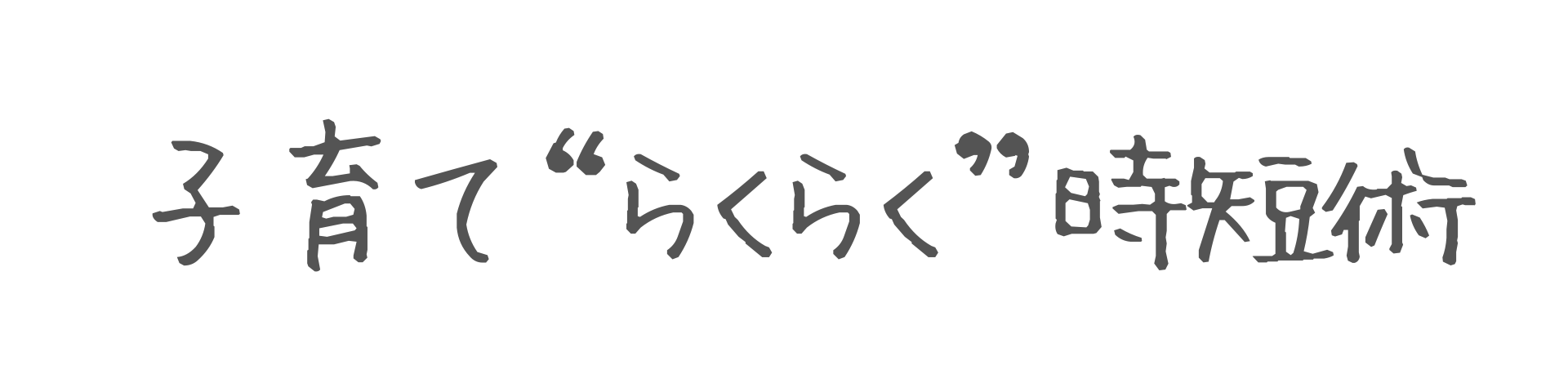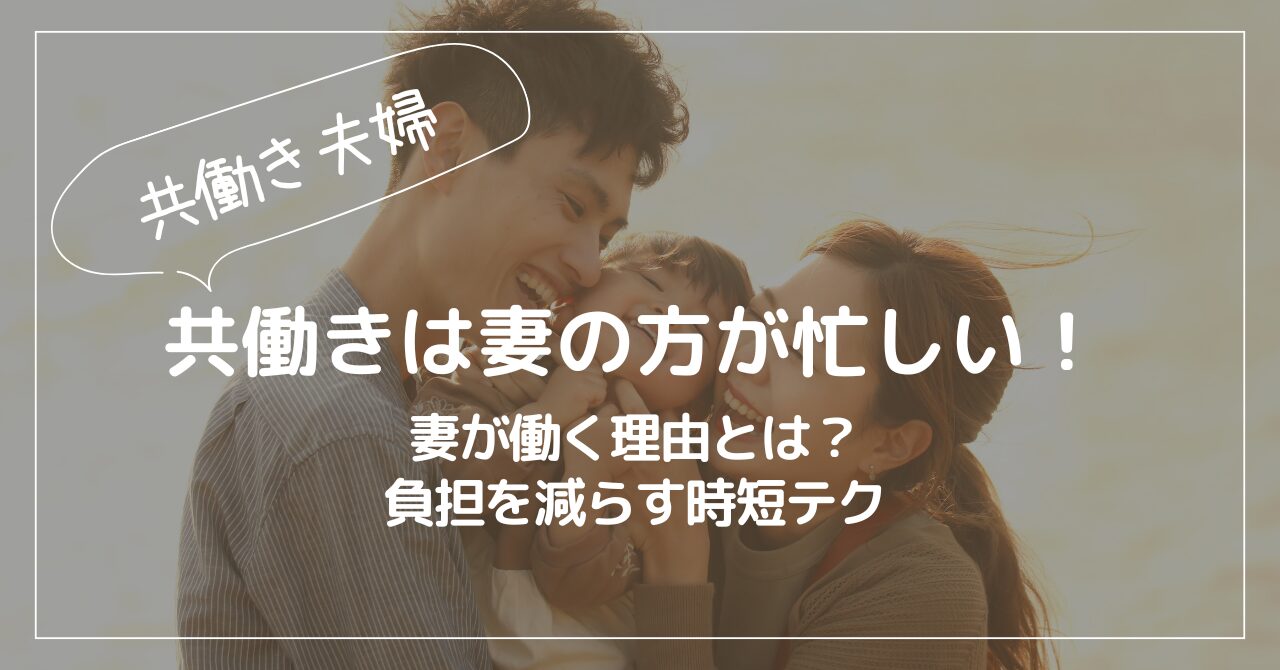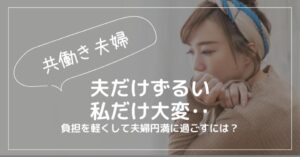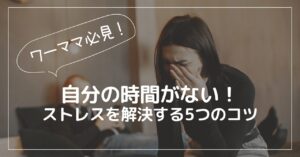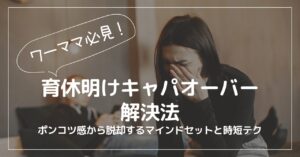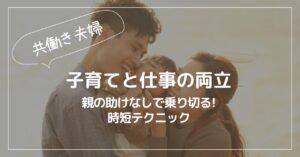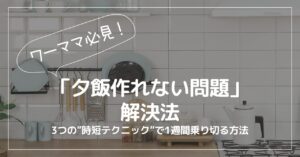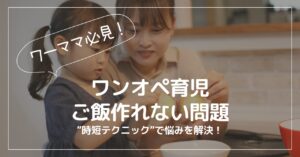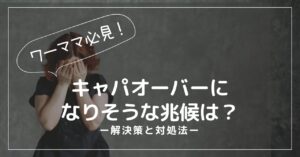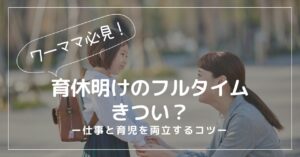「共働きなのに、妻の方が忙しいのは納得いかない」「もう疲れて限界!共働きで妻が働く理由は何ですか?」
共働き家庭では妻に負担が集中しがちな現状があります。
仕事と家庭の両立で忙しい妻が働き続ける理由は、経済的な安定だけでなく自己実現や社会とのつながりを大切にしているからです。
この記事では、共働き世帯の妻にかかる負担を軽減する、実践的な時短テクニックや家事分担のコツを紹介します。
無理なく続けられる、共働き生活のヒントになれば嬉しいです!
\家事代行・育児サポートも依頼できます/
気になったら無料カウンセリング!
共働き世帯で妻の方が忙しい理由とその実態

共働き家庭では、妻の方が忙しくなってしまうことが、少なくありません。
仕事をこなしながらも、家事や育児の大部分を担うことで、時間的にも精神的にも負担が大きくなっています
なぜこのような状況が生まれてしまうのか、その背景と実態について見ていきましょう。
共働き家庭における役割分担の現状
日本の共働き世帯は年々増加し、今や専業主婦家庭を大きく上回っています。
しかし役割分担については、従来の「性別役割意識」が根強く残っているのも事実です。
夫婦ともにフルタイムで働いていても、家事・育児の大半は妻が担うことが多い、という家庭も少なくありません。
内閣府の調査によれば、共働き家庭における家事時間は、妻が1日平均約5時間に対し、夫は約1時間という大きな差があります。
「ワンオペ育児」という言葉が広まるほど、社会問題化しています。
フルタイムで働きながら、家庭も切り盛りする妻たちの負担は、想像以上に大きいものです。
妻の担当・・・日常的に繰り返し行う調理や洗濯、掃除などの時間がかかる作業は妻が担当
夫の担当・・・「ゴミ出し」や「電球の交換」など、単発的な作業を担うケース
このような役割分担の偏りは、結果的に妻の自由時間を奪い、ワークライフバランスを崩す原因となっています。
妻が家事と仕事の両方で負担を抱える背景
妻が仕事と家庭の両方で、負担を抱える背景には、いくつかの社会的・文化的要因があります。
- ①男は仕事、女は家庭、という考え方
-
日本社会に根強く残る「男は仕事、女は家庭」という伝統的な、性別で役割分担する意識があります。
共働きになっても「家事は女性の仕事」、という意識が無意識のうちに働き、夫婦間での分担の不公平に繋がっています。
- ②出産・育児の負担
-
女性は出産や育児のために、仕事を調整せざるを得ないケースが多く、これが「家庭のことは女性が中心」という流れを強化しています。
時短勤務やフレックスタイムの活用が普及して、女性が利用しやすい環境が整ってはきていますが、一方で男性の育休取得率は、まだまだ低い状況です。
- ③女性の「完璧主義」
-
女性のなかには、「きちんとした家事」をしなくてはいけない、という意識やこだわりがある方も多くいます。
これは良いことではありますが、ワーママにとっては自分でハードルを上げてしまう事にも繋がってしまいます。
手を抜くことの罪悪感から、無理をしてでも家事をこなそうとするケースが少なくありません。
- ④親世代の影響
-
母親の姿を見て育った女性は、「母親らしさ」のロールモデルが自分の中に存在しています。
そのため、自分も母親と同じように家事をこなすべき、と考えがちです。
これらの様々な要因が複合的に作用してしまい、共働きであっても妻に家事育児が集中してしまう、という状況が生み出されています。
妻の方が忙しくなりがちな5つの要因
妻が夫よりも忙しくなりがちな、具体的な要因を5つ挙げてみましょう。
- マルチタスクの常態化
女性は、複数のことを同時に進行する傾向があります。 例えば「料理をしながら洗濯物を回し、子どもの宿題を見る」といった具合です。 効率的に見えますが、常に何かをしている状態は、休息時間の確保を難しくします。 - 見えない家事の存在
献立を考える、買い物リストを作る、子どもの学校行事を把握するなど、目に見えない家事の多くは妻が担っています。 これらの「メンタルロード」は、時間だけでなく精神的エネルギーも消費します。 - 職種や勤務形態の違い
女性は育児との両立のために、時短勤務や柔軟な働き方を選ぶケースが多く、結果的に「時間がある方」として家事の多くを担うようになります。 しかし実際には、仕事の負担も軽減されるわけではありません。 - 「助けて」と言いにくい心理的障壁
多くの女性は「自分の仕事は自分でこなすべき」という考えから、負担が大きくても助けを求めにくい傾向があります。 夫に頼むことで「できない妻」と思われることへの抵抗感もあるでしょう。 - 社会的期待とプレッシャー
「ワーキングマザー」には「仕事も家庭も完璧にこなす」というイメージが付きまといます。 周囲からの期待に応えようとするあまり、無理をして両立しようとする女性は少なくありません。
これらの要因が重なり、共働き家庭において妻の方が忙しくなりがちです。
この状況を改善するには、まず実態を夫婦で共有し、互いの負担を理解することから始める必要があります。
夫婦で話しやすい環境を作る、常に夫婦で相談して決める、という環境作りも大切ですね。
\家事代行・育児サポートも依頼できます/
気になったら無料カウンセリング!
妻が働く理由とは?経済面だけじゃない3つの動機


妻が働く理由①経済的な安定
共働きを選ぶ最も一般的な理由は、経済的な安定です。
現代社会では、一人の収入だけで家計を支えることが難しくなっています。
住宅ローンや教育費など、家庭の大きな出費を考えると、二人分の収入は大きな安心感をもたらします。
特に子どもの教育にかかる費用は年々増加傾向にあり、塾や習い事、将来の大学進学を考えると、共働きは必然的な選択となるケースが多いです。
また経済的に自立していることで、「自分のお金」を持つ安心感も重要です。
自分で稼いだお金で自分や家族のために使える自由は、女性の自己肯定感にも繋がります。
さらに将来への備えという観点も見逃せません
老後の資金計画や万が一の際の保険として、妻が独自の収入源を持つことは家族全体のセーフティネットを強化します。
特に近年は「人生100年時代」と言われる中で、長期的な視点での経済計画が重要になっています。
共働きは、家庭の経済基盤を安定させる合理的な選択です。
妻が働く理由②自己実現とキャリア形成
多くの女性にとって、仕事は単なる収入源ではなく、自己実現の場でもあります。
特に専門的なスキルや資格を持つ女性は、その能力を活かし続けたいという強い意欲を持っています。
長い教育期間や訓練を経て身につけたスキルを手放すことは、大きな喪失感を伴います。
また、仕事を通じて成長する喜びも大きな動機です。
新しい知識の習得や課題解決の達成感は、日々の充実感につながります。
昇進や評価を得ることで得られる自己効力感は、家庭生活だけでは得られない満足感をもたらすことも多いでしょう。
「子どもにも自分の夢を追い続ける姿を見せたい」という思いから働き続ける女性も増えています。
子どもにとって、仕事を通じて活き活きと自己実現する母親の姿は、将来のロールモデルとなりますね。
妻が働く理由③社会とのつながりを持ち続けること
家庭に閉じこもらず、社会とのつながりを保つことも働く大きな理由のひとつです。
職場での人間関係や社会との接点は、精神的な健康にも良い影響を与えます。
多様な価値観や考え方に触れることで視野が広がり、「母親」「妻」以外の自分自身のアイデンティティを保つことができます。
「○○さん」として認められる場所があることは、自己肯定感の維持にとても重要です。
また、社会の一員として貢献している実感も大切です。
自分の仕事が誰かの役に立っている、社会に価値を提供していると感じられることは大きな喜びとなります。
さらに家庭以外の居場所があることで、家庭内の問題を客観的に見る余裕も生まれます。
職場での人間関係は、困ったときに相談できる社会的ネットワークにもなるなど、家族以外の人間関係を持つことは、人生の安全網を広げることでもあるのです。
大切なのは、それぞれの選択を尊重し、パートナー同士が理解し合うことです。
共働きは妻の方が忙しい!家事分担の見直し3ステップ
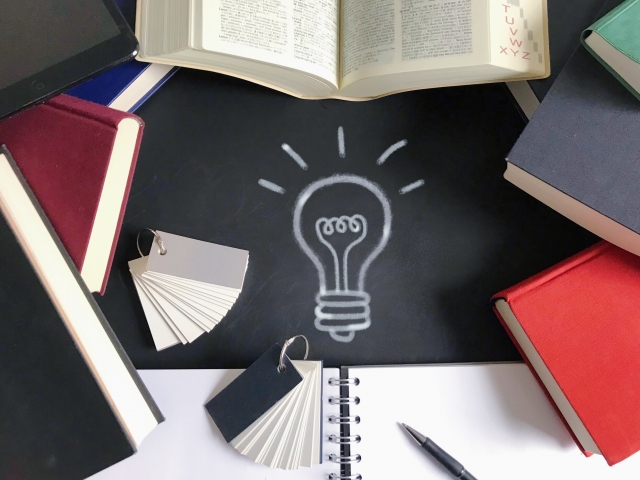
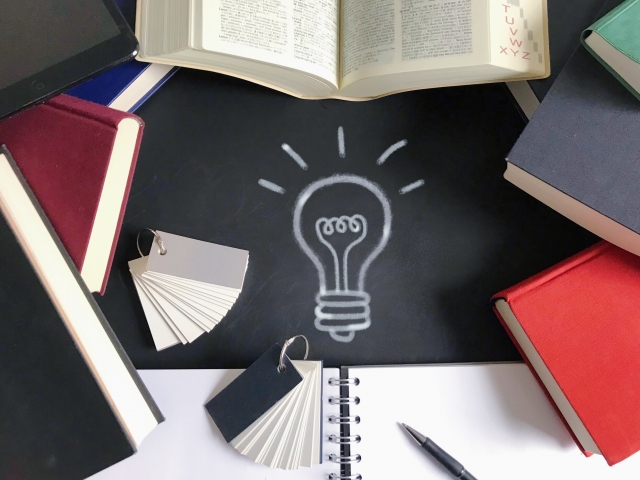
共働き夫婦が家事の負担を公平に分かち合うことは、お互いの充実した生活のために不可欠です。
ここでは、家事分担を見直すための具体的な3つのステップをご紹介します。
夫婦で協力して、無理なく続けられる家事分担の仕組みを作りましょう。
①夫婦間のコミュニケーションを円滑にする方法
家事分担の見直しをする第一歩は、素直で率直なコミュニケーションです。
不満や要望をためこまず、建設的な対話を心がけましょう。
まず大切なのは「非難しない」対話です。
「あなたは何もしてくれない」という責めるような言い方ではなく、「私は毎日料理をするのが大変だと感じている」というように、今の現状と、それに対する自分の気持ちを伝えることが効果的です。
具体的に、どうやってお願いすればいいのかな?
「〇〇をしてほしい」という明確なリクエストが効果的!「何か手伝って」という曖昧な言い方よりも、「今日の夕食の準備をお願いできる?」というように、具体的に伝えてみよう。
対話のタイミングも重要で、お互いに疲れている帰宅直後や寝る前ではなく、休日の朝などお互いの余裕がある時間を選びましょう。
定期的に「家族会議」の時間を決めておくと、問題が大きくなるまえに解決できることが多いので、おすすめです。
最後に、「相手へ感謝の言葉を伝える」ことを忘れないようにしましょう。
「ありがとう」の一言が、次の行動へのモチベーションになります。
「やり方が違って気になる」「つい口を出したくなる」という気持ちは、一旦抑えましょう。
完璧を求めすぎないことも、うまく分担できるコツです。
②家事の「見える化」で負担を公平に分ける工夫
家事の負担を公平に分けるには、まず「見える化」をしてみましょう。
目に見えない家事も含めて全体像を把握することで、より公平な分担が可能になります。
夫は、見えない家事を分かっていないことがほとんどです!
まずは、家事リストを作成しましょう。
日常的に行う家事をすべて書き出し、それぞれにかかる時間や頻度、負担度を評価します。
このとき「献立を考える」「買い物リストを作る」など目に見えない家事も、忘れずに含めることが大切です。
次に、現状の分担状況を確認します。
「誰が、どの家事を、どれくらいの頻度で行っているか」を可視化することで、負担の偏りが明確になります。
夫婦一緒にすることで、お互いがどんな家事をしていたか、分かりやすくなります。
カレンダーやタスク管理アプリで共有するのも、効果的です。
「今日は、誰が何をするか」が明確になるので、「やるつもりだった」という言い訳を防ぐことができます。
また、子供も巻き込んで、家事ポイント制を導入するのもおすすめです。
家事の難易度や時間によってポイントを設定して、ご褒美などを決めると、大人も子供もゲーム感覚で取り組めるので、続けやすくなります。
家事リストや分担は、定期的に見直しをして、仕事の繁忙期など状況に応じて柔軟に調整すると、負担の偏りも防ぐことができます。
③得意分野を活かした効率的な役割分担
家事分担を長続きさせるコツは、お互いの得意分野や好みを活かした役割分担です。
ポイントは、無理なく続けられる仕組み作りです。
- ポイント①「得意・不得意」「好き・嫌い」を共有
-
「料理が好き」「アイロンがけが苦手」など、互いの傾向を知ることで、自然な役割分担が見えてきます。
苦手な家事を無理に担当すると長続きしないため、素直に伝えることが大切です。
- ポイント②時間帯による分担
-
朝に余裕がある方が朝食準備と片付けを担当し、夜に早く帰宅する方が夕食を担当するなど、生活リズムに合わせた分担を考えましょう。
- ポイント③「日替わり制」や「週替わり制」で分担
-
「平日は妻が料理、週末は夫が料理」などルールを決めることで、どちらかに負担が集中するのを防ぎます。
また子どもが大きくなれば、家族全員での分担も検討しましょう。
役割を分担するときは、「一連の流れ」も明確にしておくことも大切です。
何をどこまでやるかが分かっていると、あとで「やった、やらなかった」という事になりません。
ただし、体調不良、仕事の繁忙期など、状況にあわせて柔軟に助け合えるようにしましょう!
共働きは妻の方が忙しい?負担を軽減する時短テクニック


共働き生活で感じる、時間の不足と疲労感。
毎日の家事に追われ、自分の時間が持てないと感じていませんか?
ここでは、実際に多くの女性が実践して、効果を感じている時短テクニックをご紹介します。
家事の効率化につながる時短家電の活用法
家事の負担を減らすには、賢く家電を活用するのがカギです。
最新の時短家電は、単なる便利グッズではなく、生活の質を大きく向上させる、強い味方になります。
- ロボット掃除機
-
今や多くの家庭に浸透していますが、使い方次第で効果は大きく変わります。
毎日決まった時間に自動稼働するよう設定しておけば、床掃除の手間がほぼゼロになります。
特に出かける前に稼働させておくと、帰宅時にはきれいな床でリラックスできます。
最新のモデルは障害物を賢く避け、部屋の隅々まで掃除してくれます。
リンク - 食洗機
-
手洗いの場合、1日あたり約30分を費やすと言われていますが、食洗機なら準備と片付けを含めても、10分程度で済みます。
年間では、約120時間の節約になるという調査結果もあります。
また水の使用量も手洗いの約1/6と節約になり、経済的メリットも大きいです。
リンク - 調理家電
-
電気圧力鍋は、調理時間を大幅に短縮するだけでなく、放置できるため同時に他の作業ができます。
例えば肉じゃがなら、通常40分かかるところ、20分程度に短縮できます。
朝にセットしておけば、帰宅後すぐに温かい料理が食べられるのも魅力です。
リンク - 衣類スチーマー
-
アイロンがけより手軽で、シワを伸ばしながら消臭効果もあります。
朝の忙しい時間に、前日着た服を軽くスチームするだけで、清潔感のある状態になります。
特にワイシャツなど、手間のかかる衣類のケアが簡単になります。
新しい家電を試す前に、まずは現在の家事の流れを振り返ってみましょう。
どの作業に時間がかかっているかを見極め、そこに特化した家電から導入するのがおすすめです。
すべてを一度に変える必要はなく、少しずつ自分の生活に合ったものを取り入れていくことが長続きのコツです。
平日と休日でメリハリをつけた家事スケジュール
毎日同じように家事をこなそうとすると、疲労がたまり、精神的にも良くありません。
まず平日は、最低限の家事に絞ること。
食事の準備と片付け、洗濯、簡単な掃除程度にしてみましょう。
例えば、子どもの服を前日に選んでおくだけでも、朝の慌ただしさが軽減されます。
- 料理は休日に作り置きをしておくと、平日の食事の準備がラクになります
- 選択は「溜めない・分けない」を基本に、毎日少しずつ洗えば、休日のまとめ洗いが減らせます
- 毎日少しずつ「ながら掃除」をすると、汚れが溜まりにくくなります
- 掃除道具は、目に付きやすくて使いやすい場所に置いておくと、自然に掃除ができるようになります
休日は、少し時間をかけて、平日にできなかった家事をまとめて片づけてしまいましょう。
窓拭き、床拭き、シーツ交換など、手間がかかる家事は、集中すると効率も良くなります。
休日は、何時までにやる!と決めて、時間を意識してやりましょう。
時間を区切ることで、集中して家事をこなすことができます。
外部サービスを上手に利用して時間を確保する
夫婦で家事を分担しても、すべての家事をこなすには、限界があります。
そんな時は、賢く外部サービスを活用して、貴重な時間を確保しましょう。
- 食材宅配サービス
-
買い物時間の大幅削減に役立ちます。
週に1回まとめて届けてもらえば、毎日のスーパーへの往復が不要になります。
最近では献立付きのミールキットも充実しているので、調理時間も短縮できます。
例えば20分程度で本格的な夕食が完成するセットも多く、料理の負担を軽減できます。
- クリーニングの集配サービス
-
特に大物の洗濯物や冬物のコートなど、自宅で扱いにくいものは専門家に任せましょう。
集荷と配達を利用すれば、店舗に行く時間も節約できます。
長期保管サービスを利用すれば、シーズンオフの衣類の収納スペースも確保できて一石二鳥です。
- 家事代行サービス
-
週に1回2時間程度の利用でも、掃除や洗濯など基本的な家事がカバーできます。
金額は1回あたり5,000円〜1万円程度ですが、得られる時間と心の余裕を考えれば十分元が取れるでしょう。
全てをお任せする必要はなく、苦手な部分だけを依頼する方法もあります。
- ネットスーパー
-
スマホから数分で注文でき、指定した時間に届けてもらえるため、買い物にかかる往復時間や店内での商品探しの時間が不要になります。
また、衝動買いを避けられるため、家計管理にも効果的です。
リピート注文機能を使えば、いつも購入する品目をワンタッチで注文できます。
- 一時保育やファミリーサポート
-
週に1回数時間だけ子どもを預けることで、集中して家事をこなしたり自分の時間を確保したりできます。
地域によっては無料や格安で利用できるサービスもあるため、自治体の情報をチェックしてみましょう。
外部サービスを利用する時のポイントは、コストパフォーマンスを考えることです。
単に料金の安さだけでなく、節約できる時間や精神的な負担軽減も含めて、総合的に判断しましょう。
最初から多くのサービスを導入するのではなく、最も負担に感じている部分から少しずつ試してみることをおすすめします。
1つのサービスに慣れてから次に進むと、生活の変化にも対応しやすくなります。
共働きの先輩ママたちに学ぶ!成功事例とは


家事負担を減らして夫婦関係を改善!
「家事は女性がするもの」という固定観念から抜け出し、夫婦で協力して家庭を運営している事例を紹介します。
「家事のプロセスの可視化」が効果的
大阪の山田さん(42歳)の家庭では、家事の内容を紙に書き出し、壁に貼っておくことで、誰が何をしているかが一目でわかるようにしました。
特に、子どもが小さい頃は、「見えない家事」の存在に夫が気づいていなかったそうです。
例えば子どもの習い事の準備や学校行事の対応など、時間はかかるけれど目に見えにくい作業の多さに夫は驚いたといいます。
週末の「家事タイムトライアル」で関係改善に成功
共働きの中村さん夫婦(共に35歳)は、日曜の午前中に二人で同時に家事を始め、どれだけ早く終わらせられるかを競うゲーム感覚の取り組みです。
最初は1時間半かかっていた作業が、工夫と協力で45分まで短縮できるようになりました。
この成功体験が自信につながり、平日の家事分担もスムーズになったそうです。
家電を活用した共同作業の仕組みづくりに成功
名古屋の鈴木さん(36歳)は、例えば洗濯機と乾燥機の使い方を夫に丁寧に教え、夫が帰宅後に洗濯物を乾燥機に移す担当になりました。
最初は細かく指示を出していましたが、次第に任せられるようになり、妻の負担が大幅に減りました。
家電の使い方を共有することで、誰でも家事ができる環境を整えたのがポイントです。
これらの事例に共通するのは、一気に完璧を目指すのではなく、小さな変化から始めている点です。
単に作業を分担するだけでなく、お互いの状況や気持ちを理解し合うことが大切ですね。
どの家庭も最初から上手くいったわけではなく、試行錯誤を重ねながら自分たちに合った方法を見つけていったということです。
家事分担は単なる作業の振り分けではなく、家族の協力体制を作る第一歩。
負担の軽減だけでなく、お互いを尊重し合える関係づくりにつながるという点も、大きなメリットといえるでしょう。
仕事と家庭の両立を実現するためのマインドセット
共働き生活を続けるには、効率的な家事テクニックだけでなく、心の持ち方も大切です。
先輩ママたちが実践している思考法を見ていきましょう。
「完璧主義を手放す」ことが第一歩
東京在住のIT企業勤務・田中さん(39歳)は、育児と仕事の両立に悩んでいた時期がありました。
家事も育児も仕事も完璧にこなそうとし、常に疲労困憊の状態で転機となったのは、尊敬する先輩からの一言。
「8割できていれば十分。残りの2割にこだわって疲れ果てるくらいなら、その時間を自分のために使いなさい」というアドバイスを受け、考え方を変えました。
例えば掃除は「見えるところだけ」に絞り、料理も時には市販品を活用するようになりました。
すると不思議なことに、家族からの不満はなく、むしろ田中さん自身の笑顔が増えたことで家庭の雰囲気も良くなったそうです。
完璧を目指すことを手放した結果、全体的な満足度が上がった好例です。
「優先順位をはっきりさせる」ことも大切
兵庫県の医療関係者・伊藤さん(41歳)は、常にTODOリストを持ち歩いています。
やるべきことを「今日必ずやること」「3日以内にやること」「いつかやること」の3つに分類しています。
特に効果的なのは、朝の時点で「今日のトップ3」を決めておくことだそうです。
これだけは必ず達成するという目標を明確にすることで、日々の満足感が大きく変わったと言います。
「助けを求めることは弱さではない」という認識
福岡県の渡辺さん(37歳)は、長年一人で家事をこなしてきました。
しかし出産後、一人で全てをこなすことの限界を感じ、夫や周囲に助けを求めるようになりました。
最初は頼ることに罪悪感がありましたが、「一人で全てやろうとするほうが無理がある」と考え方を転換しました。
専業主婦の母親世代とは環境が違うことを認識し、現代の共働き家庭に合った方法を模索したのです。
これらの事例から見えてくるのは、共働き生活を続けるには「現実的な期待値の設定」が欠かせない、ということです。
理想と現実のギャップに悩むのではなく、今の状況でできる最善の方法を選ぶ柔軟さが大切です。
一人で抱え込まず、周囲のサポートも受け入れる気持ちも大切!
そして何より大切なのは、自分自身の心と体を大切にするという基本姿勢です。
家族のために疲れ果ててしまっては、末転倒。
適度に力を抜き、長く続けられる生活スタイルを構築することが、真の「両立」といえるでしょう。
まとめ|共働きは妻の方が忙しい?互いに支え合うことが大切!


共働き世帯の生活は、それまでの暮らしと比べて挑戦の連続ですが、工夫と協力があれば充実した日々を送ることができます。
重要なのは、完璧を目指すのではなく「自分たちの家庭に合った方法」を見つけること。
他の家庭と比較するのではなく、自分たちのペースで少しずつ改善していく姿勢が大切ですね。
また家事負担の軽減は「妻一人の課題」ではなく、家族全体で取り組むべき課題です。
夫婦で率直に話し合い、互いの状況を理解し合うことから始めましょう。
まずは、自分の家庭環境や価値観に合ったものを選んで、少しずつ試してみてくださいね。
\家事代行・育児サポートも依頼できます/
気になったら無料カウンセリング!