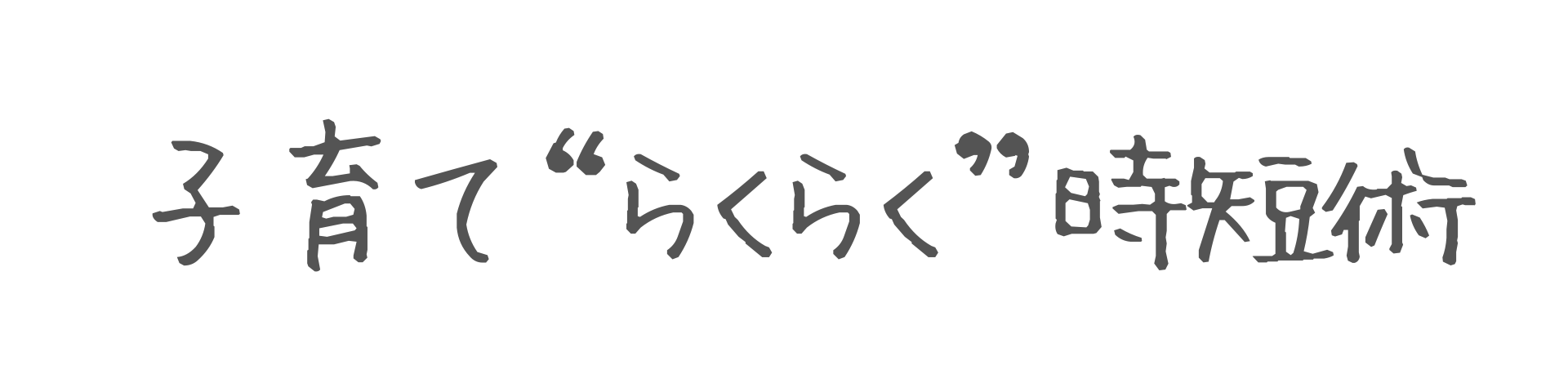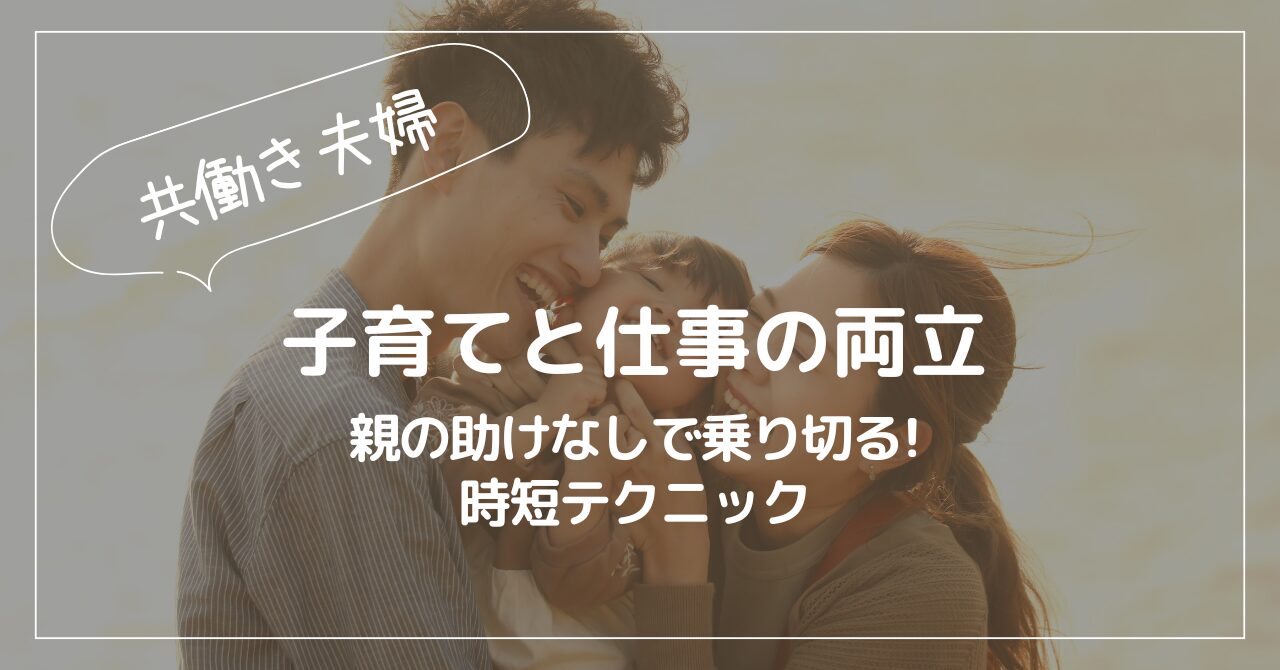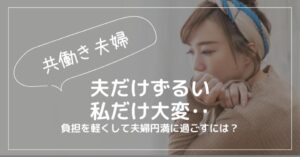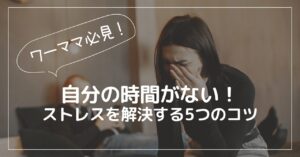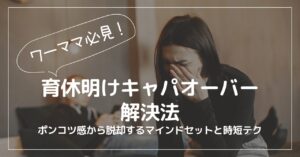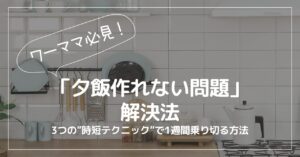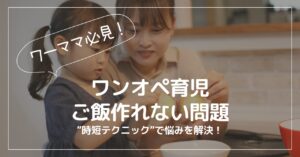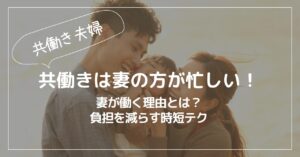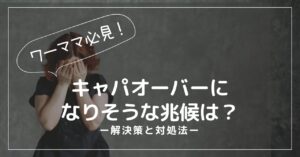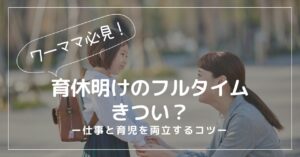「子育てと共働き、親の助けなしで両立できるか心配・・」「周りは親の助けがあって羨ましい、どうやって乗り切ればいいの」
親元から離れて暮らす共働き家庭にとって、子育てと仕事の両立は大きな課題です。
子育てを両立させるには、限られた時間を最大限に活用する工夫と、効率的な家事育児の分担が重要なポイントになります。
この記事では、親のサポートがなくても共働き家庭が実践できる、具体的な時短テクニックや家族で協力するコツを紹介しています。
\家事代行・育児サポートも依頼できます/
気になったら無料カウンセリング!
子育てと共働きを両立する前に知っておきたい心構え

親の助けなしで子育てと仕事を両立させるには、「心構え」が大切です。
まずは自分たちの状況を受け入れ、前向きに考えるところから始めましょう。
正しい心構えがあれば、日々の育児や家事も効率的に進められます。
親の助けなしでも前向きに考えるメリット
親の助けなしで子育てをしている状況に不安を感じる方も多いでしょう。
周りの友人が、実家の両親に頼っている姿を見ると、羨ましく感じることも・・
でも、実は親の助けなしで子育てをすることには、多くのメリットがあるんです。
メリット①自分たちのペースで子育てができる
親世代と、子育ての価値観が異なることも多いですが、自分たちだけで子育てをすれば、夫婦で話し合って決めた方針で一貫した子育てができます。
子どもにとっても、一貫したルールの方が理解しやすく、安心できる環境が作れます。
メリット②子どもとの絆が深まる
毎日の送り迎えや食事、お風呂など、すべての時間を子どもと過ごすことで、子どもの小さな変化に気づきやすくなります。
子どもの成長過程を細かく見守れる喜びは、親にとっては大きな財産ですね。
メリット③夫婦の協力関係が強まる
親に頼れない分、夫婦で協力して家事や育児を分担する必要があります。
そのため夫婦のコミュニケーションが深まり、お互いを尊重しあえる関係が築けます。
子どもにとっても両親が協力する姿は、良いロールモデルになるでしょう。
親に頼れない分、困りごとや苦労も多くはなりますが、家族で乗り越えた経験が自信となり、絆が深まります。
親の姿を見ている、子どもの自立心育成にも役立ちます!
自分たちのペースで子育てするコツ
親の助けなしで、自分たちのペースを守りながら子育てするためには、いくつかのコツがあります。
①完璧を求めない
まず大切なのは、「完璧を求めない」という姿勢です。
家事も育児も、100点満点を目指すと疲れ切ってしまいます。
特に共働きの場合は時間的制約があるため、「これくらいでOK」というラインを夫婦で話し合って決めておくと、心に余裕が生まれます。
「平日の夕食は30分で作れるメニューに限定する」「リビングの掃除は週末だけにする」など、優先順位をつけて必要最低限のことだけやる、と割り切ってみましょう。
子どものためと思って、あれもこれもと手を広げすぎると、結局は親の疲労が子どもにも悪影響を及ぼしてしまいます。
②ルーティーン化
毎日、同じ時間に同じことをする習慣をつけると、子どもも親も動きやすくなります。
朝の準備、夕食、お風呂、寝かしつけなど、一連の流れを決めておくと、無駄な時間がぐんと減ります。
例えば、朝は「起床→着替え→朝食→歯磨き→準備確認→出発」という流れを毎日同じにすると、子どもも自然とその流れに乗れるようになります。
小さな子どもでも、ルーティンがあれば、安心して行動できるようになるものです。
③子どもの力を借りる
子どもは、手伝いをしたがる時期があります。
その意欲を活かして、年齢に合った家事を任せることで、子どもの成長を促しながら親の負担も減らせます。
子どもが一人でできるまで、親の負担は増えますが、一時的なものです!子どもができるようなった時には、かなり助かりますよ。
3歳ごろからできる簡単なお手伝いには、おもちゃの片付けやテーブル拭き、タオルなどの洗濯物を畳むお手伝いなどがあります。
5歳ぐらいになると、簡単な料理の手伝いや、自分の身の回りのことを自分でする習慣をつけられるでしょう。
子どもにとっても、できることが増える喜びを感じられる機会になります。
④自分の時間を確保する
自分よりも家族、子どもを優先してしまうママは、少なくありません。
親の助けがない分、ママの疲れもたまりやすいため、意識的に自分をリフレッシュする時間を作りましょう。
子どもが寝た後の1時間を自分の時間にする、週末に夫婦交代で2時間ずつ自由時間を取るなど、工夫次第で息抜きの時間は作れます。
共働き家庭の子育てを楽にする家事の時短テクニック


共働きで、親の助けなしの子育ては、時間との戦いです。
限られた時間で効率よく家事をこなすために、時短テクニックを取り入れてみましょう!
工夫次第で家事の負担を大幅に減らして、子どもとの時間や自分の時間を確保することができますよ。
平日の家事を最小限に抑える方法
平日は仕事と子育ての両立で、時間に余裕がありません。
この時期の家事は、割り切って「必要最低限」を心がけましょう。
掃除・洗濯
洗濯は乾燥機付き洗濯機を導入すると、洗濯ものを干す時間が削減できます。
部屋の掃除も完璧を求めず、平日はよく使うリビングとキッチン、トイレのみを重点的に掃除するといいでしょう。
モップなどを使えば、気になった時にサッと掃除ができます。
ロボット掃除機を導入すれば、昼間に掃除をしてくれるので、ストレスも時間も軽減できます。
料理
食事の準備は、特に時間がかかる家事です。
夕食の準備時間を短縮するコツとして、週末に下ごしらえをしておく方法があります。
肉や野菜を切って冷凍しておけば、平日は解凍して調理するだけで済みます。
また、電子レンジや圧力鍋などの時短調理器具を活用すれば、調理時間が大幅に短縮できます。
手の込んだ料理は週末に作り、平日は15~20分で作れるシンプルなメニューに絞ってみましょう。
買い物
買い物も時間がかかる家事の一つです。
スマホアプリを使って買い物リストを作成し、週に1~2回まとめて買い物をする習慣をつけるといいでしょう
最近はネットスーパーも充実しており、時間指定で自宅まで届けてくれるサービスも便利です。
仕事帰りに毎日スーパーに立ち寄る時間を省ければ、その分子どもと触れ合う時間が増やせます。
何より大切なのは、「今日やらなくても良いこと」を見極める目です。
例えば、床の掃除は明日でも問題ない、アイロンがけは週末にまとめてする、など優先順位を明確にしておくと心に余裕が生まれます。
週末にまとめて行う効率的な家事術
平日の時間的制約から解放される週末は、まとめて家事をこなすチャンスです。
効率よく進めるコツを押さえておきましょう。
作り置き
「作り置き料理」は、効率的な週末の定番家事です。
まとめて複数のおかずを作り置きしておけば、平日の夕食準備が格段に楽になります。
煮物、マリネ、サラダ、ミートソース、カレーなどは、作り置きの定番メニューです。
保存容器に小分けして冷蔵庫に保管しておけば、平日は温めるだけで食卓に並べられます。
作り置き初心者なら、まずは2~3品から始めて、徐々に増やしていくのがおすすめです。
大掃除
「大掃除」も、週末にまとめて行いましょう。
家族全員で分担すれば、1~2時間程度で終わらせることができます。
子どもも年齢に合った掃除の手伝いを任せると、家族で協力する意識が育ちます。
例えば掃除機をかける、拭き掃除をする、トイレ掃除をするなど、家族で分担を決めておくと効率的です。
子どもには、小さいうちからお手伝いの習慣をつけておくことで、将来的には家事の一部を任せられるようになりますよ。
来週の準備
週末は「来週の準備」をする時間でもあります。
家族のスケジュールを確認して、必要な準備をしておきましょう。
子どもの学校行事や習い事の確認、仕事の予定の共有などを行い、必要なものをリストアップしておけば、平日の慌ただしさが軽減されます。
例えば子どもの幼稚園や保育園の持ち物を、週末にまとめて準備しておくと、平日の朝の忙しさが緩和されます
お弁当が必要な日の献立も、前もって考えておけば、買い物リストに必要な食材を加えられます。
時短家電を活用して家事を効率化
今では便利な時短家電が、たくさんあります。
ただ初期投資は必要になりますが、長い目で見れば時間の節約になり、家事を軽減してくれる相棒になってくれます!
ロボット掃除機
「ロボット掃除機」は、共働き家庭の強い味方です。
外出中に自動で掃除してくれるため、掃除の時間を大幅にカットできます。
最新モデルなら、外にいてもアプリを使って操作が可能です。
食洗器
「食洗機」も、時短家電の代表ですね。
食後の片付けが格段に楽になるのはもちろん、節水効果も期待ができます。
コンパクトなタイプもあるので、キッチンスペースが限られている賃貸住宅でも、検討の価値があります。
自動調理器
材料を入れてボタンを押すだけで、調理が完了する電気圧力鍋や低温調理器は、手間が省けて柔らかく、食べやすく調理ができます。
また火を使わないため、安全性も高く、子どもが小さい家庭でも、安心して使えます。
乾燥機付き洗濯機
「乾燥機能付き洗濯機」も、時短につながります。
天候に左右されず洗濯物を乾かせるため、いつでも洗濯することができます。
特に、梅雨時期や冬場は大活躍です。
また、干す必要がなくなるので、その分時間が短縮できます。
家電の導入にあたっては、使用頻度や家族のライフスタイルに合わせて選んでみましょう。
すべてを一度に揃える必要はなく、優先度の高いものから徐々に導入していくのがおすすめです。
親の助けなしで子育てと共働きを両立させる食事作り


食事の準備は、毎日の大きな負担になりがちです。
親の助けがなくても効率的に栄養バランスの取れた食事を作るには、計画的な食事管理が欠かせません。
時短しながらも、健康的な食生活を維持するコツを紹介します。
作り置きで平日の食事準備を時短する
作り置き料理は、共働き家庭の救世主です!
週末や休日に、まとめて調理しておけば、平日の食事準備が格段に楽になります。
煮物、マリネ、ミートソース、カレー、スープなどは冷蔵で3、4日、冷凍なら2~3週間ほど保存できます。
初めからたくさんの種類を作ろうとせず、まずは夕飯作りのついでなどで、1~2品から始めてみるといいですね。
効率よく作り置きをするコツは、調理の順番を工夫することです。
例えば、オーブン料理を先に始め、その間に煮物を作り、さらにその間に和え物を準備するという具合に、複数の料理を同時進行で作ることで時間を短縮できます。
- 保存容器を使い分ける
-
保存容器は、使いやすさと保存性を考慮して、選びましょう。
耐熱ガラス容器は電子レンジでそのまま温められ、におい移りも少なくて便利です。
小分けして冷凍保存する場合は、一食分ずつラップで包んでからジップロックに入れる方法も、おすすめです。
- 作り置きはローテーションを決めるとラク!
-
献立のローテーションを決めてしまうと、メニューを考える手間が一気にラクになります。
「月曜日は冷凍しておいたカレー、火曜日は作り置きの煮物とサラダ」というように、あらかじめ献立を決めておくと食材の無駄が減り、買い物リストも作りやすくなります。
慣れてきたら、子どもの好みや年齢に合わせた作り置きメニューを増やしていけば、レパートリーが広がって飽きがきません。
子どもが小さい家庭なら、野菜をペースト状にして冷凍しておけば、解凍してスープやソースに混ぜ込んで手軽に栄養バランスが取れますね。
子どもと一緒に楽しめる簡単調理のコツ
食事の準備を、子どもとのコミュニケーションを取れる時間にするのもおすすめです。
子どもは料理を手伝うことで達成感を得られ、さらに食への関心を高めることができます。
子どもの年齢にあわせて、野菜を洗う、材料を混ぜる、といった簡単なことから始めると良いですね。
時間がある週末には、子どもと一緒に楽しめるメニューを取り入れると、さらに親子の絆も深まります。
例えば、ホットケーキやピザ、おにぎりなど、形を作る料理は、子どもが喜んで参加してくれるメニューです。
子どもが作った料理は、多少形が悪くても、たくさん褒めてあげましょう。
「自分で作った」という満足感が、偏食の改善にもつながることがあります。
また、子どもの自己肯定感もあがり、今後の成長にも役立ちます。
親子クッキングをするときは、時間に余裕をもって取り組みましょう。時間がないと、親に余裕がなくなってイライラしたり、子どもを焦らせてしまい、逆効果です。
週末の午前中など、ゆったりとした時間を選んでチャレンジしてみてくださいね。
栄養バランスを考えた時短レシピ
忙しい毎日でも、栄養バランスは疎かにできませんよね。
短時間で作れて、栄養価の高いレシピを知っておくと、便利で役立ちます。
- 「ワンプレートメニュー」
-
ワンプレートは、時短の強い味方です!炒め物、サラダ、ご飯などを一皿に盛り付ければ、洗い物も減らせます。
色とりどりの野菜を使えば見た目も華やかになり、子どもの食欲もアップします。
- 「具だくさんスープ」
-
栄養満点の、時短メニューです。野菜、肉、豆類などをたっぷり入れれば、これ一品でバランスの良い食事になります。冷凍野菜を活用すれば、下ごしらえの時間も省けます。
- 「簡単丼もの」
-
炒めた具材をご飯にのせるだけの簡単料理ですが、具材を工夫すれば栄養バランスも取れます。
肉や魚と野菜を組み合わせた親子丼やマーボー丼は子どもにも人気です。
- 「常備菜の活用」
-
例えば常備菜の筑前煮に卵を加えれば親子煮に、マリネした野菜にツナとマヨネーズを加えればサラダに変身します。
一つの常備菜を違うアレンジで提供することで、メニューのバリエーションが広がります。
献立には「赤・黄・緑」をうまく取り入れると、栄養面でバランスが取れます。
タンパク質(赤)、炭水化物(黄)、ビタミン・ミネラル(緑)をバランスよく摂ることを心がけましょう。
忙しい日は、冷凍野菜や缶詰も上手に活用して、不足しがちな野菜を補いましょう。


\ 初回限定1,850円オフ! /
2回目以降はいつでもスキップ・解約が可能


子育てと仕事の両立を支える外部リソースの活用法


地域や社会には、様々なサポート制度があります。
これらを上手に活用することで、親の助けが得られない場合でも、子育てと仕事の両立がぐっと楽になります。
外部リソースを賢く使いこなすコツを見ていきましょう。
親の助けがなくても利用できる地域サポート
自治体による子育て支援サービスは、親の助けがない家庭にとって大きな味方となります。
多くの場合、無料または低料金で利用できるサービスが充実しています。
- 「ファミリー・サポート・センター」
-
地域の援助会員と、利用会員をつなぐシステムです。
保育園の送迎や放課後の預かりなど、細切れの時間でも柔軟に対応してもらえます。
料金は地域によって異なりますが、比較的リーズナブルな場合が多いです。
- 「病児・病後児保育」
-
子どもが体調を崩した時に頼れるサービスです。
親が仕事を休めない場合でも、看護師が常駐する専用施設で子どもを預かってもらえます。
こちらも事前登録制のところが多いため、冬の風邪シーズン前などに登録しておくと良いでしょう。
- 「一時預かり保育」
-
急な仕事や用事ができた時に、短時間子どもを預かってもらえます。
事前登録が必要な場合が多いので、利用する可能性がある場合は早めに登録しておくと安心です。
- 「子育て支援センター・児童館」
-
未就学児とその保護者が、気軽に利用できる施設です。
子どもの遊び場としてだけでなく、専門スタッフに子育ての相談ができる点も心強いポイントです。
特に土曜日も開館している施設であれば、共働き家庭でも利用しやすいでしょう。
子どもを通じて、親同士の交流ができることもあり、情報交換をしたり、交流に繋がることもあります。
これらのサービスを利用する際のポイントは、複数のサービスを組み合わせることです。
例えば「平日は保育園、土曜日は児童館、急な残業時はファミサポ」というように、状況に応じて使い分けると、心強いサポート体制ができあがります。
シッターやファミサポなどの外部サービス
民間のサービスも、親の助けのない家庭には、頼もしい存在です。
費用はかかりますが、柔軟性や専門性の高さがメリットです。
- 「ベビーシッター」
-
自宅での保育が可能なため、子どもの生活リズムを崩さずに済みます。
特に夜間や早朝、休日など保育園が対応していない時間帯に重宝します。
信頼できるシッターを見つけるコツは、大手の派遣会社を利用することです。
研修を受けたシッターが派遣されるため、安心して任せられます。
- 「家事代行サービス」
-
共働き家庭の家事負担を減らせる選択肢のひとつです。
掃除、洗濯、料理など家事全般を代行してくれるサービスで、週1回の利用でも家事の負担がかなり軽減されます。
特に小さい子どもがいる時期は、限られた時間を家事ではなく子どもとの時間に使える点が大きなメリットです。
- 「送迎サービス」
-
保育園や習い事への送迎を代行してくれるサービスで、親の勤務時間と保育園の開所時間が合わない場合に、活用できます。
ファミリー・サポート・センターでも送迎は対応していますが、民間サービスの方が時間の融通が利く場合があります。
これらのサービスを利用する際は、費用対効果を考慮しましょう。
例えば、「家事代行は毎日でなく週1回にして、主要な家事だけを任せる」「作り置きを中心にお願いする」など、予算に合わせた使い方がおすすめです。
また「共働き家庭向け割引」や「定期利用割引」を設けているサービスもあるため、複数のサービスを比較検討してみましょう。
\家事代行・育児サポートも依頼できます/
気になったら無料カウンセリング!
職場の制度を最大限に活用するコツ
親の助けがない分、職場の制度を最大限に活用することも重要です。
近年は働き方改革の流れもあり、子育て世代を支援する制度が充実してきています。
- 「時短勤務」は小学校入学前まで利用できる企業が増えています。
フルタイム勤務と比べて給与は減りますが、子どもとの時間を確保できる点ではメリットが大きいです。
夫婦で交互に時短勤務を利用する方法もあります。 - 「フレックスタイム制度」も子育て世代には便利です。
出社時間を調整できれば、朝の保育園送りも余裕ができます。
帰宅時間も調整できるため、子どもの習い事の送迎なども対応しやすくなります。 - 「テレワーク・在宅勤務」が可能な職場なら積極的に活用しましょう。
通勤時間が削減できるだけでなく、子どもの急な体調不良にも対応しやすくなります。
完全在宅でなくても、週1~2回のテレワークでも家事や育児の負担軽減につながります。 - 「有給休暇の計画的取得」も大切です。
子どものイベントや長期休暇に合わせて計画的に休暇を取得すれば、親の助けがなくても子どもと充実した時間を過ごせます。
夫婦で交互に休暇を取れば、長期休暇中の子どもの面倒も見やすくなります。 - 「育児目的休暇」や「子どもの看護休暇」など、子育て特有の休暇制度も積極的に利用しましょう。
これらは法定の制度であり、取得を理由に不利益な扱いを受けることはありません。
職場の制度を活用する際のポイントは、「早めの相談」です。
突然の申し出ではなく、余裕を持って上司や人事部に相談することで、円滑に制度を利用できるようになります。
また同僚への配慮も忘れず、自分が休む際のフォロー体制を事前に整えておくと良い関係を保てます。
共働き家庭の子育てにおける夫婦協力のコツ


親の助けがなくても、夫婦二人で乗り越えられる子育ての秘訣があります。
お互いを思いやり、工夫を重ねることで、共働き生活と子育ての両立は可能です。
一緒に協力して、子育てを楽しむためのヒントをご紹介します。
親の助けが羨ましいと感じない分担方法
誰かに頼れない状況でも、夫婦で上手に分担すれば、子育ては十分乗り切れます。
大切なのは、二人で協力しあう気持ちと工夫です。
親の助けがある家庭を羨ましく思うことは自然なこと。
でも実は、夫婦だけの子育てには夫婦だけの良さがあります。
二人だからこそ、密なコミュニケーションが生まれ、育児方針も統一しやすくなるメリットもあるのです。
- 完璧を目指さない
-
最初に大切なのは「完璧を目指さない」という心構え。
家事も育児も100点を狙わず、「これくらいできていれば十分」というラインを夫婦で相談して決めましょう。
例えば、毎日の掃除は諦めて週末にまとめて行う、料理は簡単なものでOKと割り切るなど。
- 得意・不得意で分ける
-
具体的な分担方法として効果的なのが「得意・不得意で分ける」方式です。
夫が料理好きなら食事担当、妻が段取り上手なら子どものスケジュール管理を担当するなど。
苦手なことを無理に押し付けると不満が溜まってしまうため、お互いの得意分野を活かした分担にするのが理想的です。
- 時間帯で分ける
-
朝と夜の時間帯での役割分担も効果的。
例えば、朝は妻が子どもの支度、夫が朝食と弁当作り。
夜は夫が子どものお風呂、妻が夕食準備というように時間帯で分けることで、双方の負担が見える化されます。
- 感謝の気持ちを伝え合う
-
何より重要なのは、「感謝の気持ち」を伝え合うこと。
「今日も仕事お疲れさま。子どもと遊んでくれてありがとう」など、当たり前のことでも、言葉にして伝えましょう。
感謝の言葉は疲れた心を癒し、モチベーションになります。
分担を形にするために、家事育児のタスクボードを作り、見える化するのも良い方法です。
冷蔵庫などに貼れる予定表に、「ゴミ出し:夫」「洗濯:妻」など、担当者を明記します。
終わったタスクにチェックを入れると達成感も生まれます。
夫婦の強みを活かした育児分担術
夫婦それぞれの個性や特技を子育てに取り入れると、子どもにとっても親にとっても充実した時間になります
パパとママは性格も趣味も違って当然。
その違いこそが、子どもの成長に良い影響を与えます。
二人の強みを組み合わせることで、バランスの良い子育てが実現します。
例えば、運動神経が良いパパなら体を使った遊びを担当。絵本の読み聞かせが得意なママならお話の時間を受け持つ、などです。
子どもは両親から異なる刺激を受けることで、多様な経験をすることができます。
- 職業スキルを育児に活かす視点も有効
-
例えば、営業職のパパなら人との関わり方を教える、事務職のママなら整理整頓や計画性を伝えるなど。
職場で培ったスキルは、意外と子育てに応用できることが多いものです。
また、「パパの読み聞かせ、楽しそうだね」「ママのお弁当、いつもおいしそう」など、相手の良さを子どもの前で言葉にすることで、両親のやり取りから多くのことを学びとってくれます。
- お互いの時間を把握しておくことも大切
-
例えば「妻は水曜の夜にヨガ教室」「夫は土曜の朝にジョギング」など、リフレッシュタイムを確保し合うことで、育児のモチベーションも上がります。
何より、「この家族にしかない子育て」を楽しむ気持ちが大切!
親の助けがなくても、夫婦二人の個性を活かした独自の子育てスタイルが、子どもにとっては何よりの宝物になります。
コミュニケーションで育児ストレスを軽減する方法
子育ての悩みや不安は、誰にでもあるものです。
夫婦間の上手な伝え方と聞き方で、ストレスを軽減し、より良い関係を築きましょう。
子育ての大変さは経験した人にしか分からないもの。だからこそ、パートナーとの対話が重要です。
思いを溜め込まず、思っているや感じていることを素直に伝えることで、ストレスは軽減されます。
まず大切なのは「定期的な夫婦会議」の時間を設けること
子どもが寝た後の15分でも構いません。
「最近の子どもの成長」「気になること」「お互いへの要望」などを話し合う時間を作りましょう。
話し合いのコツは「責めない」こと。
「あなたは全然手伝わない」ではなく「洗濯物を畳むのを手伝ってもらえると助かる」など、具体的な要望として伝えましょう。
否定的な表現より、肯定的な表現の方が相手に伝わりやすいものです。
聞く側の姿勢も大切で、スマホを見ながらではなく、しっかり目を合わせて聞くこと。
「それは大変だったね」「そう感じたんだね」など、共感の言葉を返すと、話した方は理解してもらえたと感じます。
今の気持ちを「素直に」伝えること
育児の悩みを伝える時は「今どんな気持ちか」を素直に表現しましょう。
「子どもが言うことを聞かなくてイライラする」「仕事と育児の両立で疲れている」など、素直な気持ちを伝えることが解決の第一歩です。
言わなくても分かって!という気持ちでは、相手に伝わることはありません。
クールダウンの時間も大切
もし話し合いが平行線になったら、一度クールダウンの時間を取ることも大事。
「今日はここまでにして、また明日話そう」と区切りをつけ、冷静になってから再度話し合うと良いでしょう。
子どもの成功体験を共有する
小さな成功体験を共有することも、ストレス軽減に効果的です。
「今日、子どもが自分でスプーンを使えたよ」「初めて『ありがとう』と言ったよ」など、喜びを分かち合うことで、育児の楽しさを再確認できます。
LINEなどで写真を送ったり、「熱が下がってきたよ」「トイレができたよ」などの短い文章を送り合って情報共有するのも、効果的です!
夫婦2人の時間を大切にする
夫婦だけの時間を大切にすることも、忘れないようにしましょう。
月に一度でも良いので、二人だけのデート時間を作りましょう。
子育ての話題以外で会話することで、「親」ではなく「パートナー」としての関係も育まれます。
親の助けが得られない場合、夫婦2人の時間が持てない方が多いですが、各種サポートなどを利用して、2人の時間を作るようにしましょう。
コミュニケーションの目的は、「完璧な解決策を見つけること」ではなく「互いを理解し合うこと」。
必ずしも答えが出なくても、気持ちを分かち合えるだけで心は軽くなります。
まとめ|親の助けなしでも充実した子育てライフを送るために


親からの支援がなくても、工夫と夫婦の協力で、豊かな家族時間が築けます。
二人三脚の子育ては大変ですが、その分夫婦の絆、家族の絆を深まってきます。
特に意識したいのは、「比較しない」という姿勢です。
親の助けがある家庭、シッターさんを雇える家庭など、それぞれの家庭に異なる条件があります。
大切なのは、自分たち家族の幸せの形を探すこと。
他の家庭と比べるのではなく、昨日の自分たちより今日の自分たちが少しでも笑顔になれば、それが成功です。
今日からできる、小さな一歩を踏み出しましょう。
\家事代行・育児サポートも依頼できます/
気になったら無料カウンセリング!